感染症予防のポイント・相談窓口
マスク着用の考え方について
マスクの着用について、令和5年3月13日以降は、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることになります。個人の意思に反しマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。

【厚生労働省】マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて(PDFファイルへのリンク)
日常生活では【手洗い】を!咳が出るときは【咳エチケット】を!
新型コロナウイルスは、飛沫感染や接触感染により、うつるといわれています。また、2022年3月28日、国立感染症研究所においては、空中に浮遊するウイルスを含むエアロゾル(空中に数分から数時間にわたって浮遊する、小さな粒子や乾燥した粒子)を吸い込むことによって感染する「空気感染」も原因のひとつであるとの見解が加えられました。
| 飛沫感染 | 感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。 |
|---|---|
| 接触感染 | 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。 |
| 空気感染 | 空中に浮遊するウイルスを含むエアロゾルを吸い込むこと |
実際にどの経路で感染するのかは、感染者から放出される感染性ウイルスを含む粒子の量や環境条件によって決まり、必ずしもどれか1つであるとは限りません。
日常生活では、まず【手洗い・マスクの着用】と、【密集・密着・密接の3密を避けること】が大切です。また、咳が出るときは必ず【咳エチケット】を守ってください。
詳しい消毒・除菌方法も厚生労働省ホームページに掲載されています。
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染経路について(厚生労働省ホームページ)
厚生労働省『診療の手引き』では、医療機関向けではありますが、最新の情報が随時更新されています。
感染対策に口腔ケアと鼻呼吸も!
ロ腔ケア(歯磨き)
インフルエンザウイルスやコロナウイルスなどは、まず口もしくは鼻から体内に入ると、鼻の奥やのどの粘膜に付着します。その後、細胞内に入り込み、そこで増殖して感染します。
加えて、お口の中にいる歯周病菌などの細菌も、ウイルスが細胞内に入りやすくすることが分かっています。つまり、おロの中が不潔で細菌の数が多いと、ウイルスが体内に入る危険性が高くなるということであり、お口の中をきれいにしておけばインフルエンザやコロナウイルス感染のリスクを低くすることができると言えます。
起きている間は、ウイルスや細菌などに対する防御因子が含まれている「唾液の力」である程度守られていますが、眠っている時というのは、唾液がほとんど止まるため、夜間、そして朝起きてすぐのおロというのは最も細菌が増えた状態になっており、感染リスクが高まります。
そのため、寝る前の歯磨きは特に念入りに行いましょう。
鼻呼吸
鼻呼吸は、鼻毛などの動きによって異物やウイルスが取り除かれるため、風邪やインフルエンザへの感染リスクが下がります。また、鼻で加温・加湿された空気がのどに入るため、のどの粘膜がダメージを受けにくくなります。
マスクを着用していると、暑さや息苦しさから口呼吸になりやすくなります。
口呼吸の場合、のどに直接、影響が及ぶので、ウイルスが体内に侵入しやすくなります。
町民の皆様におかれましては、今後も、口腔ケアや意識的な鼻呼吸を加えた、感染対策をお願いいたします。
大台町主催のイベント・講演会における感染防止対策
- 会場では、手指消毒液を設置し手洗いや消毒、換気など基本的な感染防止対策に努めること。
- 発熱や咳等の風邪のような症状のある方に参加自粛の協力を要請すること。
- マスクの着用については、国が示す基本的対処方針に準ずること。(詳しくは、このページ上部に掲載しています。)
- 高齢の方や基礎疾患をお持ちの方で感染リスクを心配される方は、参加自粛の協力を要請すること。
- 3つの密「密閉・密集・密接」の会場環境とならぬよう留意すること。
- 参加したイベントで感染が発生した場合、保健所などの聞き取りに協力を要請すること。
※今後、感染拡大が進んだ場合、適宜見直すものとします。
イベントの中止や延期については、防災行政無線等でもお知らせいたします。
その他の詳細については、各担当課までお問い合わせください。
発熱など症状がある方の受診方法
相談・受診の前に心がけていただきたいこと
- 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。
- 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。
- 基礎疾患(持病)をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話でご相談ください。
医療機関にかかるときのお願い
- 複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の医療機関を受診することはお控えください。
- 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いいたします。
発熱、咳などの症状がある場合
まずは、かかりつけ医などの身近な医療機関に、電話でご相談ください。
相談する医療機関に迷う場合は、「受診・相談センター」へご相談ください。
診療時間や受診方法などが通常と異なる場合がありますので、受診前に電話にてご相談ください。
相談先の案内に従って受診してください。
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様、かかりつけ医や受診・相談センターに早めにご相談ください。
小児については、小児科医による診察が望ましく、かかりつけ小児医療機関や受診・相談センターに電話などでご相談ください。
受診・相談センター
〇24時間対応(土・日・祝日も対応)・・・松阪保健所 電話番号:0598-50-0518
陽性が判明した場合
新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(三重県ホームページ)
三重県のパンフレットをご確認ください。外出の注意点・ごみ・清掃・食事等の注意点を掲載しています。
新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口
新型コロナウイルスに関する一般的な相談
国(厚生労働省)・・・フリーダイヤル:0120-565653
ワクチン接種に関する相談
みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン
電話番号:059-224-2825
- 土・日・祝含む午前9時から午後9時まで
- 電話での相談が難しい場合は、メール(vaccine@pref.mie.lg.jp)またはファックス(059-224-2344) でご相談ください。
夜間窓口
電話番号:050-3185-7947
- 21時から翌9時まで(土・日・祝日も対応)
- AI音声技術を活用した自動応答電話窓口です。
新型コロナウイルスワクチン副反応相談窓口
電話番号:059-224-3326
インターネット・ポータルサイト(小児への新型コロナウイルスワクチン接種に関する副反応相談窓口):https://covid19-vaccine.mie.jp/news/post-4318/
- 24時間対応(夜間、土曜日、日曜日、祝日を含む)
- 新型コロナウイルスワクチン接種前後の副反応に関する質問や相談の窓口です。
- 対応言語(日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語)



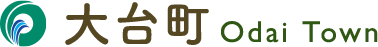




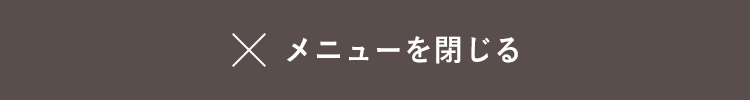
更新日:2023年07月24日