【受付期間は終了しました】令和6年度・定額減税に伴う「調整給付」のご案内
「調整給付」については支給終了となっています。令和7年度において、本制度に基づく「不足額給付」が実施予定となっています。
「不足額給付」は、1.令和6年中の収入の確定に伴い、所得税額や扶養人数も確定したことに基づき、2.改めて本定額減税の仕組みに基づいて『所得税分の減税額』を算出し、3.令和6年に実際に給付した『調整給付額』と比較した結果、4.なお減税しきれなかった額がある方
等が給付対象となります。
その他詳しくは判明次第ご案内します。
調整給付金は、9月以降、確認書到着分から順次給付しています
2024年度の調整給付金は次のとおり振込ました。
- 確認書が、9月2日までに到着した分:9月9日
- 確認書が、9月11日までに到着した分:9月18日
- 確認書が、9月20日までに到着した分:9月30日
- 確認書が、10月1日までに到着した分:10月8日
- 確認書が、10月10日までに到着した分:10月18日
- 確認書が、10月21日までに到着した分:10月28日
- 確認書が、10月31日までに到着した分:11月8日
- 確認書が、11月11日までに到着した分:11月18日
大台町の支払日は原則「8のつく日」で、8日が土日祝日の場合、翌日以降となります。
令和6年度 調整給付の確認書を8月23日に発送しました
住民税と所得税の定額減税において【減税しきれない方】に給付する『調整給付』のお知らせは、8月23日に発送しました。10月31日までに、同封の『確認書』を提出してください。町が確認書を受理した日から2週間を目安に給付金を振り込みます。
同封書類は…
- 【調整給付金 支給確認書】…【定額減税補足給付金(調整給付金)のお知らせ】と一体になっていますので、半面を切り取って、「確認書」側の書類を提出してください。
- 【確認書の記入について】…確認書の記入が必要な箇所について案内している文書です。提出する必要は、ありません。
- 【返信用封筒】…確認書の提出にお使いください。
「確認書」の記入について
確認書では、給付金額と振込先の口座を確認いたします。提出いただく書類と書き方例は、次のとおりです。
すでに口座情報の登録がある方
【口座登録の“ある”方】確認書の記入について(PDFファイル:1.4MB)
マイナンバー制度による「公金受取口座」での登録のある方や、過去の給付金において実績が記録されている場合、その口座情報をあらかじめ印字した確認書をお送りします。
記載内容を確認し、「氏名・確認日・連絡先電話番号」を記載いただき、【確認書】のみ返送してください。
ただし、記載されている口座と異なる口座への振り込みを希望される場合は、その内容を記載し【口座番号のわかる書類】を添付し、提出してください。
口座情報の登録はない方
【口座登録の“ない”方】確認書の記入について(PDFファイル:1.4MB)
給付実績や公金口座登録がない方(注1)は、振込先の口座情報を入力いただき、【確認書】、【口座番号のわかる書類】、【本人確認書類】を添付して提出してください。
(注1):町の税金等を口座振替している情報は、引き継いでいません。例えば、公金口座登録は未登録で、町の税金等の振替登録はあるものの、転入直後などで過去に給付実績がない方は、口座情報の記載がありませんのでご注意ください。
代理申請となる方
対象者本人以外の口座に振り込みを希望される場合は代理人申請として取扱います。確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】欄へ記入いただき、【本人確認書類】には、本人と代理人の2人分の書類を添付し、提出してください。
調整給付のポイント
- 定額減税における1人あたり40,000円(住民税10,000円、所得税30,000円。以降扶養1人につき同額を加算)の仕組みをもとに算出します。
- 1.【住民税分】として、令和6年度“住民税の所得割(注記1)分”から、実際に減税しきれていない金額
2.【所得税分】として、“令和6年度の住民税情報をもとに推計した所得税(推計所得税といいます)分”から、減税しきれない額(注記2)
1.と2.の合計額の、1万円未満を切り上げた数字が調整給付額です。 - 調整給付における所得税分の計算は、推計所得税によって給付対象かどうかを算出します。
実際に所得税が源泉徴収されているかいないか、納税しているか還付されているかは関係なく、令和6年度に課税した住民税の情報から推計することになっています。 - 本人の状況(扶養人数や障害者控除など)によって、住民税所得割や推計所得税どちらかだけが減税しきれなかった(住民税所得割課税、推計所得税は0円)場合、0円となっている税は全額引ききれなかったものとして加算します。
例:減税額は、2人(扶養1人)=住民税所得割20,000円が可能で、推計所得税60,000円が可能とします。
課税されている額は、令和6年度住民税所得割が16,000円。左記課税情報からの推計所得税は0円とします。
この場合、引ききれなかった額=住民税所得割4,000円、推計所得税60,000円となり、64,000円の1万円未満切り上げ=70,000円の調整給付額となります。
住民税の内訳は、「均等割」と「所得割」となっています。
「均等割」は、所得金額が一定以上の方へ、一律、課税されます。
一方で所得割は、所得に対して、社会保険料や医療費などの所得控除を行った残額の10%を課税します。
今回の定額減税は、この「所得割」に対して減税を行うため、年間6,000円が課税されているものの(それは均等割の金額であるために)定額減税の対象外となる方も存在します。
所得税は、通常、個人ごとの1月から12月までの収入や経費をまとめて、その翌年に確定申告等で税額が決まる税金です。
令和6年中の収入に基づいて定額減税を行うのであれば、その確定は令和7年以降になります。
この場合、住民税の減税に伴う給付と、所得税の減税に伴う給付のタイミングがずれることになるため、調整給付における「所得税」は、確定ではなく推計(令和6年度課税、令和5年中の収入に基づく住民税情報)によって算出することとされました。
なお、この仕組みによって、「推計」した所得税で給付した後、「確定」した所得税の金額が推計より少なく、さらに給付すべき必要が生じたときは、「不足額給付」として、追加で給付されます。
よくある質問
Q.年金生活者ですが、給付の対象ですか?
夫婦共に65歳以上で年金生活となっている場合、その年金支給額にもよりますが、住民税が非課税となっている場合があります。
住民税も所得税も非課税であれば、減税も対象外となり、調整給付もありませんが、この制度とは別に、昨年12月に非課税世帯へ「非課税世帯への合計10万円給付」がなされていると思われます。
単身世帯の方も同様に、住民税が非課税となっていれば減税も対象外となる一方で、非課税世帯への合計10万円給付が先に行われていると思われます。
詳しい状況は個人で異なるため、お問合わせください。
Q.パートで扶養の範囲内で働いていますが、給付の対象ですか?
調整給付額があるかどうかは、住民税所得割と推計所得税それぞれを算出して判定します。
(住民税所得割分)年間の収入がそのパート給与収入のみとして計算すると、年間103万円を超えてきたときは、給与を受ける本人が扶養をしている人数等にもよりますが、住民税所得割が課税になる場合があります。
この場合、所得割の額に応じた「定額減税」が実施され、定額減税では引ききれない場合は調整給付の対象となります。
(給与収入130万、扶養なし、社会保険料や生命保険料も控除なしの場合、住民税所得割は29,500円、住民税均等割は6,000円になります。同条件で給与収入が103万円の場合、住民税所得割は2,500円、住民税均等割は6,000円になります。)
(推計所得税分)住民税と所得税の計算方法に違いがあるものの、年間103万円を超えてきたときは、所得税も課税になる場合があり、給与収入が年間130万円でも定額減税しきれないことになると思われます。
(給与収入130万、扶養なし、社会保険料や生命保険料も控除なしの場合、所得税額は13,500円。同条件で所得税額が課税となる給与収入は103万1千円以上になります。)
このことから、概ね、103万を超えない範囲では調整給付も定額減税も対象外であり、103万円を超えてくる場合は調整給付の対象となる可能性があると思われます。
令和6年度課税の根拠となる、ご自身の給与収入については、個人宛の納税通知でご確認ください。このほか、詳しい状況は個人で異なるため、お問合わせください。
Q.所得税の減税はいつされますか?
会社等に勤めていて、「扶養申告」をして「源泉徴収されている」場合は、その扶養人数に応じた定額減税が実施されます。一方で、扶養申告のない、報酬や一時的な日当なども源泉徴収されますが、この場合は定額減税されません。
自営業の場合、確定申告の際に定額減税を計算することになります。ただし、予定納税をされている方は、第1期分からその額が反映されることになります。
自営業者の方で予定納税がある場合の定額減税は、国税庁へ申請が必要な場合もありますので、詳しくは、国税庁のホームページもご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
これら源泉徴収における定額減税は、調整給付とは別の仕組みにおいて実施されます。
Q.所得税が推計であるならば、令和5年中に限って大きな収入があったのですが、その計算はどうなりますか?
推計所得税は、令和6年度住民税課税(令和5年中)の収入に基づきます。
その大きな収入がなければ調整給付が受けられるような収入の状況だったとしても、この場合では、住民税所得割も推計所得税も減税しきれて(引ききれて)しまうことになり、調整給付については、対象外となります。
一方で、本制度では「不足額給付」という、令和6年中の収入(令和7年度住民税課税)で最終的に計算した結果、「給付しきれていない方」に対する追加の給付を予定しています。
令和5年中に限って大きな収入があった方は、この不足額給付によって給付対象となる可能性があると思われます。
大きな収入があったときの翌年の追加の給付(不足額給付)となる例
令和5年中は、土地の長期譲渡所得1,000万円、年金収入200万円、支払った社会保険料20万円、65歳以上の単身世帯。年金収入は令和5年中も令和6年中も同額。令和5年中には譲渡所得があり、令和6年中には無かったとします。減税可能額は、住民税所得割で10,000円、所得税で30,000円です。
- (令和6年3月ごろ)長期譲渡所得を含めた令和5年中の収入にかかる確定申告を行い、実際の所得税額1,511,000円を納税します。
- (令和6年6月)住民税所得割に、減税後の504,500円(減税額10,000円)が課税されます。【住民税分の定額減税が終了。調整給付は対象外】
- (令和7年3月ごろ)令和6年中の確定申告を行います。年金収入のみで計算すると所得税の所得税額が11,000円となります。この時点で、推計でない所得税が算出されたため、改めて定額減税を実施、11,000円-30,000円となり、納税額は0円になります。【所得税分の定額減税が終了】
- (令和7年6月以降予定)減税しきれなかった19,000円が明らかとなっているため、「不足額給付」が実施されます。
補足:不足額給付については、大きな収入の差額に限らず、急な収入の減少や、扶養親族の追加(出生)も対象となる可能性が考えられます。
Q.職場の年末調整の後、確定申告をしていますが、減税や給付はどうなりますか?
調整給付については、令和5年中収入にかかる確定申告の内容が優先されます。
定額減税のうち、住民税分については、確定申告の内容で減税しています。
定額減税のうち、所得税分については、6月以降の源泉徴収において職場への扶養申告に基づいて減税がなされ、来年の確定申告において減税額の最終調整が行われることになります。
なお、受け取った調整給付金については非課税収入であり、確定申告や職場での年末調整等で記載する必要はありません。(ただし、定額減税されるべき税額は記載欄が設けられます。)
給与所得者(お勤めの方)で、調整給付の対象者となったのに、源泉徴収でも定額減税が開始される方が存在します。
一見、減税を二重に実施しているように思われますが、「調整給付(所得税分)」も「源泉徴収」も、来年の税額確定までの間に推計で実施しているものですので、税額確定の結果、減税+給付が適正な金額となるよう制度設計されています。具体例を次の回答にて掲載しています。
【源泉徴収】とは、所得税について、確定申告(もしくは年末調整)によって所得税額が確定するまでの間に、先に天引きして納めておく仕組みです。源泉徴収税額と、確定した所得税額を比較し、『源泉徴収税額が少ない場合』は、確定する時点で追加納付となり、『源泉徴収税額が多い場合』は、確定した時点で還付請求をすることになります。
Q.年末調整、調整給付、源泉徴収の関係の具体例が知りたい。
次のとおりになります。
条件は、令和5年中の給与収入1,500,000円(月支給額120,000円、賞与60,000円)、扶養無し(所得税減税可能額30,000円)、実際の所得税額20,000円だった場合で、令和6年中も給与額に変わりがない場合とします。
まず、調整給付は10,000円(30,000円-20,000円)が支給されます。
かつ、月給では最大30,000円の定額減税が行われるため、源泉徴収については0円となります。
そして、11月頃からの年末調整が行われた際に、確定する所得税額が20,000円ですが、定額減税30,000円を実施して、0円となります。源泉徴収(先払い)分は0円ですので、過不足調整はありません。
年末調整後で、減税しきれない10,000円が明らかになりますが、調整給付の時点ですでに推計所得税から算出した10,000円を給付しているため、追加給付は実施されません。
Q.住宅ローンや寄附金税額控除の確定申告をしたのですが、減税や給付はどうなりますか?
推計所得税の算出においても、ローン控除や寄附金控除は、あるものとして計算し、住宅ローンや寄附金の税額控除を行った後の住民税額に基づいて算出することになります。
Q.扶養を間違えていた、扶養が間違っているのを見つけた場合はどうしたら良いですか?
大台町役場税務住民課までご連絡ください。正しい内容に基づいて再計算を行い、減税や給付を実施します。ただし、基準日となる6月3日以前になされた扶養申告に対しての、付替えなどは応じられません。この場合は、令和7年以降の確定申告等によって可能となる場合がありますのでご相談ください。
令和5年中に退職し、現在無職です。給付はありますか?
上記『令和5年中に限って大きな収入…』と同様に考えます。
所得税分について、推計所得税の時点では「減税」の対象ですが、令和7年になってから確定する所得税は0円となる見込みで、かつ、住民税分は「減税」が実施されていると思われますので、所得税分の「給付」が、令和7年になってから行われる可能性が高いと思われます。



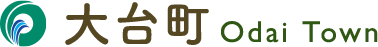




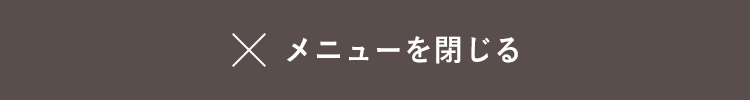
更新日:2024年12月04日