国民健康保険税のしくみと届出
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税(国保税)は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主にかかる税金です。
年税額の計算は、加入者の所得に応じて計算する『所得割』、固定資産税額に応じて計算する『資産割』、加入者数に応じた『均等割』、1世帯あたりの『平等割』の合計によって求められます。
さらに、所得割、資産割、均等割、平等割には、『医療分』『後期高齢者医療支援分』『介護保険料分(40歳以上65歳未満の方)』という、税率が異なる3つの区分も設けられており、次の表のとおり、すべての合計によって年間の税額が決まります。
年税額の算出イメージ
| 医療分 | 所得割 基準総所得の5.10% |
資産割 固定資産税額の30.00% |
均等割 1人あたり23,000円 |
平等割 1世帯あたり21,000円 |
|---|---|---|---|---|
| + | ||||
| 高齢(支援)分 | 所得割 基準総所得の2.00% |
資産割 固定資産税額の8.00% |
均等割 1人あたり7,500円 |
平等割 1世帯あたり7,500円 |
| + | ||||
| 介護分 (40歳以上65歳未満) |
所得割 基準総所得の1.40% |
資産割 固定資産税額の6.00% |
均等割 1人あたり7,000円 |
平等割 1世帯あたり5,000円 |
- 基準総所得=所得金額-43万円。たとえば、給与収入200万円の方は、計算により給与所得132万円となり、基準総所得は89万円。医療・高齢・介護の3区分の合計所得割は、75,650円になります。
- 均等割と平等割については、世帯の所得に応じて軽減措置があります。
国民健康保険の軽減(7割・5割・2割)
加入者1人あたりで算定する均等割と、加入1世帯あたりで算定する平等割は、世帯の所得が一定基準以下のとき、その基準に応じて軽減されます。
・世帯の所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下のとき・・・7割軽減(本来の3割の金額)
・世帯の所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者数及び特同一世帯所属者数)以下のとき・・・5割軽減
・世帯の所得が、43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数)以下のとき・・・2割軽減(本来の8割の金額)
※給与所得者等の数とは、納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与所得を有する者(収入金額が55万円を超える者に限る。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、65歳以上の者にあっては、当該公的年金等の収入金額が125万円を超える者に限り、給与所得を有する者を除く。)の合計数をいいます。
※特定同一世帯所属者とは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方をいいます。
加入期間と年税額について
年税額は、毎年6月に通知し、以降毎月末日を納期として10回分納となっている一方で、加入期間は翌年3月までの加入を前提としたもの(4月から加入していれば、翌年3月までの12か月加入とする)になっています。社会保険のように、毎月の納付額がそのまま1か月分の金額として算定されません。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)の施行に伴い、令和5年11月以降に出産された国民健康保険被保険者の方の国民健康保険税(所得割・均等割)を軽減します。
対象者
大台町国民健康保険に加入している方で、出産予定または出産された方
※妊娠85日以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含みます。)
対象期間
出産予定月又は出産月の前月から出産月の翌々月までの4か月間
多胎妊娠の場合は、出産月の3か月前から出産月の翌々月までの6か月間
※令和6年1月以降の保険税が軽減の対象です。
届出方法
出産予定日の6か月前から届出可能です。
健康ほけん課備え付け又はダウンロードした申請書を記入し、必要書類と併せて健康ほけん課へ提出してください。※郵送による届出も可
必要書類
・母子健康手帳等の写し(名前、分娩予定日の記載箇所が必要です。)
・世帯主および出産される方以外の方が届け出る場合は、運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の写しが必要になります。
産前産後期間に係る大台町国民健康保険税軽減届出書 (Wordファイル: 21.5KB)
年の途中に加入や喪失があったとき
年の途中で加入したり資格喪失があった場合は、その手続きをした翌月の中旬に、精算した納税通知を発送します。
このため、加入の届出が遅れた場合は、年税額は変わらないものの、納付回数が少なくなり、1回あたりの納付額が増加します。加入喪失の届け出は忘れずにお願いします。
また、資格を喪失した月は税額が反映されませんので、その月末の保険税は納付していただくことになりますのでご留意ください。(精算により納めすぎとなった場合は、後日還付通知をお送りします。)
非自発的失業(雇い止め)があったとき
職場の雇い止めに伴い、『非自発的失業』となって国民健康保険に加入した場合、税額を軽減します。
国民健康保険税は、前年1年間の所得を基に算定されるため、職場を退職して以後、翌年3月までは、現役並みの保険税を課税することになりますが、この制度では、算定における前年の給与所得を100分の30(30%)まで軽減し、年税額を算定します。
軽減を受けるためには、書類を持参のうえ、国民健康保険の加入手続きのとき等に申請してください。
必要要書類として、雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を持参してください。(離職理由コード:11.12.21.22.23.31.32.33.34であること)
※平成21年3月31日以降に失業した方で、失業時点で65歳未満の方が対象です。



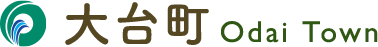




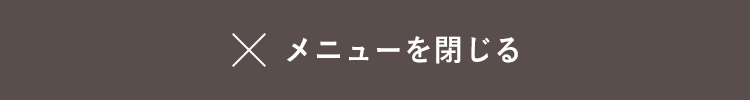
更新日:2024年06月01日