国民健康保険について
国保のしくみ
国民健康保険(国保)は、病気やケガに備えて、お金(保険税)を出し合い、安心して治療が受けられるよう助け合う制度です。
75歳未満で、職場の健康保険などに加入している人、生活保護を受けている人以外は、全員が国保に加入することになっています。
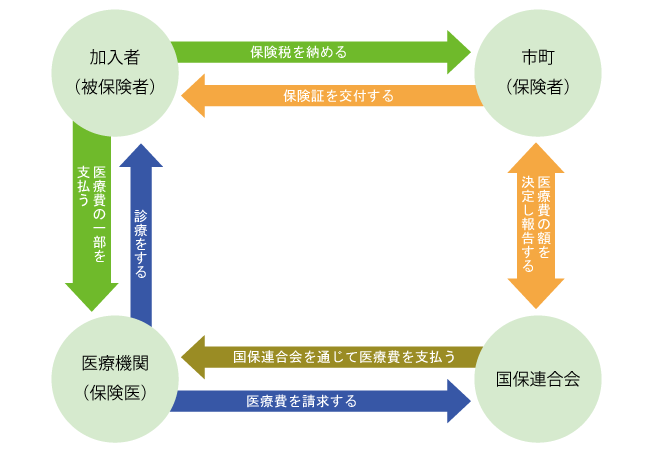
国保の加入者
- 自営業の人、農業・漁業などに携わっている人
- 退職して、職場の健康保険などをやめた人とその家族
- パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人
- 住民票に記載されている外国籍の人で職場の健康保険に加入していない人
70歳以上になると
国保に加入している人が70歳になると、国保の保険証とは別に、『高齢受給者証』が交付され、自己負担割合が変更となります。(現役並みの所得がある方は除きます)
高齢受給者証は、医療を受けるときの自己負担の割合を示す証明書です。国保の保険証と一緒に窓口に提示してください。
高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の場合はその月)からとなります。
なお75歳になると国保から「後期高齢者医療制度」に移行します。
退職者医療制度
長年勤めた会社などを退職して、国保に加入した人が、年金受給者となったとき、65歳になるまで、本人とその家族がお医者さんにかかるときに適用される制度です。65歳になると一般の国保に加入することになります。
対象となる人
国保に加入している人で、厚生年金などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、または40歳以降の年金加入期間が10年以上ある人とその扶養家族。
対象となる日
年金の受給権が発生した日が、退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら14日以内に、保険証と年金証書を持って、役場健康ほけん課窓口まで届け出てください。「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
国保の届出 必ず14日以内にすませましょう
国保に入るとき
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 他の市区町村から転入してきたとき | 印鑑、転出証明書 |
| 他の健康保険をやめたとき | 印鑑、健康保険の離脱証明書 |
| 転入や健康保険をやめて、新たに家族の一員となったとき | 印鑑、転出証明書または健康保険の離脱証明書 |
| 他の健康保険をやめ、退職者医療制度に該当したとき | 印鑑、健康保険の離脱証明書、年金証書 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 |
| 子どもが生まれたとき | 印鑑、母子健康手帳 |
国保をやめるとき
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 他の市区町村へ転出したとき | 印鑑、保険証 |
| 他の健康保険に加入したとき | 印鑑、国保と健康保険の保険証 |
| 生活保護を受けることになったとき | 印鑑、保険証、保護開始決定通知書 |
| 死亡したとき | 印鑑、保険証、死亡証明書 |
その他
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 退職者医療制度に該当したとき | 印鑑、年金証書、保険証 |
| 退職者医療制度に該当しなくなったとき | 印鑑、保険証 |
| 住所・世帯主・氏名などがかわったとき | 印鑑、保険証 |
| 保険証を無くしたり、汚して使えなくなったとき | 印鑑、使えなくなった保険証、身分を証明するもの |
| 修学のため、子どもが他の市区町村に住所を定めるとき | 印鑑、保険証、在学証明書 |
国保で受けられる給付
給付については、別ページ「国保で受けられる給付」をご覧ください。
保険料(税)の決め方
給付の費用の財源は、保険料(税)です。
大台町は、保険税方式を採用しています。計算の方法や軽減については、別ページ「国民健康保険税」をご覧ください。
リフィル処方せんについて
リフィル処方せんとは
症状が安定している患者に対して、医師の処方により、医師および薬剤師の適切な連携の下、一定期間内・回数内であれば、その都度診察を受けなくても処方せんを繰り返し利用することができる処方せんのことです。
リフィル処方せんの仕組み
リフィル処方せんは、症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象で、処方せんの「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていれば利用できます。
投薬量に制限のある医薬品や向精神薬、湿布薬はリフィル処方せんにできません。
医療機関で処方せんを毎回もらわず、同じ処方せんを薬局で最大3回まで繰り返し使用できます。
リフィル処方せんを使うことで
医療機関を受診する回数が少なくなるため通院負担を軽減でき、結果として、医療費の軽減にもつながります。
リフィル処方せん活用の留意点
リフィル処方せんが発行されてから、1回目は通常の処方せんと同様に、処方された日から4日以内に薬局で薬を受け取ります。2回目以降については、原則、前回の調剤日を起点として、処方期間が終わる日を予定日とし、その前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
リフィル処方せんを利用している間は医療機関の受診が不要となるため、薬剤師が服薬状況を確認し、気になる点や症状に変化があれば、調剤を行わずに医療機関への受診を促します。そのため、同じ薬局で調剤してもらうことが推奨されます。



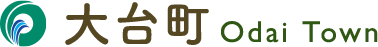




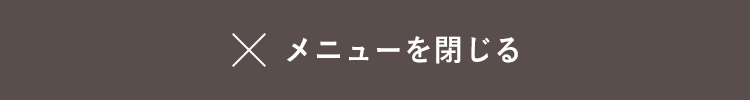
更新日:2024年07月25日